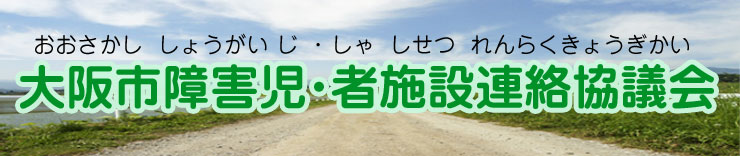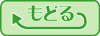障施協・知的障害者施設部会 アンケート結果
4 新事業について
通所施設全体では56%が新事業へ移行したが、中でも通所更生は61.5%と移行率が高い。一方で入所施設は27.3%しか移行していない。
「新事業(日中活動)の内容」では「生活介護事業」が54.5%と群を抜いており、続いて「就労継続支援B型」(27.3%)、「就労移行支援」(13.6%)と続く。このあたりは当初から予想された感があるが、自立訓練(生活訓練)は1施設に止まっている。また、「就労継続A型」はハードルが高いせいだろうか、移行施設は未だない。
「まだ移行していない施設の予定」では同様に「生活介護」(46.2%)、「就労継続支援B型」(23.1%)と続くが、「自立訓練(生活訓練)」(15.4%)が「就労移行支援」(7.7%)を上回っている。
「移行の過程で苦慮した点」では、「職員の確保(支援員、看護師)」や「申請事務の煩雑さ」が多くあがっている。
「移行後の感想」では、肯定的な意見として 1.収入増加による経営安定(2施設) 2.職員数の増加(1施設) 3.経験主義からの「脱却・事業目的の見直し・支援計画の充実など(1施設) 4.就労移行支援での有期限による緊張感を持った取り組み があげられている。
否定的な意見としては 1.スタッフの入れ替わりが激しく支援の質が低下 2.就労継続B型などの単価の低さ 3.事務量の増加 などがあげられている。
「まだ移行していない理由」では、1.自立支援法の動向を見守る 2.増収が見込めない という意見が多かった。
1 新事業へ移行したか
| 通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | ||||
| 移行した | 8 | 61.5% | 2 | 40.0% | 3 | 27.3% |
| していない | 5 | 38.5% | 3 | 60.0% | 8 | 72.7% |
| 合計 | 13 | 100% | 5 | 100% | 11 | 100% |
2 新事業の内容(日中活動)
| 【移行済】 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | 合計 | |
| 1.生活介護 | 8 | 1 | 3 | 12 | 54.5% |
| 2.自立訓練(機能訓練) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3.自立訓練(生活訓練) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5% |
| 4.就労移行支援 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13.6% |
| 5.就労継続支援・A型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 6.就労継続支援・B型 | 3 | 2 | 1 | 6 | 27.3% |
| 合計 | 11 | 5 | 6 | 22 | 100.0% |
| 【移行していない−予定】 | 通所更生 | 通所授産 | 入所 | 合計 | |
| 1.生活介護 | 3 | 2 | 7 | 12 | 46.2% |
| 2.自立訓練(機能訓練) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3.自立訓練(生活訓練) | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.4% |
| 4.就労移行支援 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.7% |
| 5.就労継続支援・A型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 6.就労継続支援・B型 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23.1% |
| 7.未定 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.7% |
| 合計 | 8 | 6 | 12 | 26 | 100.0% |
3 新事業へ移行した施設・事業所へ質問
1.移行する過程において苦慮した点
(旧通所更生)
・スタッフの確保
・利用者負担アップによって、利用の減少や退所の不安があった。職員が思うように集まらなかった。
・看護師の配置
・生活介護へ移行したため、人員配置基準を満たすための従業員増に苦労しました。
・ サービス利用者(及び保護者)は、移行時に施設から初めて新体系事業について説明を聞いた方がほとんど。支援法施行時に行政より何らかの説明を。
・ 経過的デイサービスがなくなるため、その利用者に迷惑をかけないようにするため、移行せざるを得なかった。
・移行期の会計処理、就労Bの会計処理等、不明な部分が多く、移行時点で十分に把握できていなかった。
・移行のための施設改修と申請事務を同時に実施したので、業務が煩雑でした。
・現場の人員不足の合間をぬって相談、申請、再提出と出向く体制がとりずらかった。
・ 旧デイサービスも生活介護へ移行したが、こちらは単位上がる反面、従来あった送迎加算のおかげで大半の人に送迎していた。旧通所更生は送迎はあまり実施していなかったので。両制度を同じ生活介護にしたとき、送迎を拡充できず、調整に苦慮した。
(旧通所授産)
・ 指定申請書の作成が難しくて大変でした。
・ 利用者への説明が難しく、新体系を選ぶのが困難な方が多かった。
(旧入所)
・ 障害認定区分の申請を早くし区分が早くから分かっていればよかった(12月から早く出していたが)。
・ 大阪府の専門の担当者でも、解釈に相違があるなど、制度そのものが非常に複雑かつ難解である。
・ 施設の経営の視点、運営管理の視点、福祉サービスの視点で踏み切ったが、旧法の時代のしがらみもあり、施設の現場では厳しい現実、局面に直面している。時代の要請とはいえ確信をもって新体系に移行できたものではない。
・ 区分の調査での調査員の理解(市町村によって大きく見解が違う)
・ 提出書類のやりとり(府担当者の中にも認識の違いがあり困った)
2.移行後の感想(良かった点、悪かった点)
(旧通所更生)
・ 経営的には安定した。
・ 非常勤職員が増えていくのは運営、支援内容の充実等で問題はあるものの、職員数が増えたことは大きなメリットです。
・ 経験主義から脱しようという気運が高まったこと、事業の目的を見直そうという動き、支援計画をもっと充実させてゆこうとする姿勢等、移行を積極的にとらえたことが良かった点です。
・ 収入面では少しだが回復した。1年更新の定額の契約しかできないので、スタッフが辞め、入れ替わりが激しく、支援の質を高めることが困難である。
・ 様々な激変緩和措置で何とかやっているが、いずれも恒久的なものではないため、利用者の個別支援計画に沿った支援の将来像が描きにくい。
・ 生活介護の平均障害程度区分をある程度維持するようにしなければ職員配置数を変えなくてはならない。
・ 就労Bの単価が低すぎること。就労Bの工賃向上に限界を感じる事。
・ その事業の目的や基準と利用者の現状に差がありすぎることが問題点です。
・ 今後の希望者が重度の人に多く、就労継続は少ないので、1年経った2008・4・1付けで定員変更申請をしています。
(旧通所授産)
・ 就労移行支援では2年間という有期限のサービスとなっており、そのことが利用者、職員とも今まで以上に緊張感をもって取り組めたような気がします。
(旧入所)
・ 3か月が経過し産みの苦しみと思っているが、福祉サービスの提供をどうしたら利用者のニーズに応えていけるか暗中模索中。
・ 利用者の入れ替えにより、重度化、高齢化し、365日24時間体制ケアの中で、救急医療の受入変化も顕著で難しい運営を日々行っているのが実感である。
・ 結果的には収入が上がった(区分調査において事前に調査員に理解を求めた。それなりの努力を要した)。
・ 事務量の増大。
・ 人員配置の拡大。
4 まだ移行していない施設への質問
1.移行していない理由
(通所更生)
・ 移行しても増収は見込めない
・ 自立支援法の動向を見守り、移行は流動的である。
・ 利用者の年限退所の為、現在のところバランスが悪く、利用者不足。
・ 移行するメリットが少ないため
(通所授産)
・ 大阪市との協議が必要(大阪市立)
・ 障害者自立支援法の今後の動向が不確実なため
・ 政策動向の一定の見極め ・障害程度区分による減収予想
(入所)
・ 法、制度を見極めるため
・ 移行しても増収は見込めない
・ 制度がまだ固まっておらず不確定要素が多いように思う。自活訓練事業の有効活用をはかりたいため。
・ 旧法のまま2年前に設立し体制を整えるために手一杯であり、他施設のアドバイス等を受けながら現在既に移行されている施設をみせていただきながら検討している。
・ 法人内調整により(現在勉強会実施中)
・ 障害程度区分が予想より低く出た(知的障害の特性が反映されていない)ため。